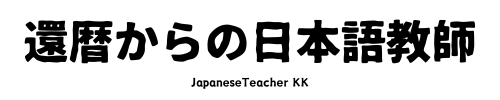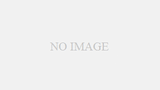日本語教師として働くには、必ずしも大学院で学ぶ必要はありません。2024年4月から始まった「登録日本語教員」の資格は、筆記試験に合格し、実践的な教育実習を修了すれば取得できます。この登録日本語教員は名称独占の国家資格で、資格を持たない人は名称を使えないものの、資格がなくても日本語を教えること自体は可能です。実際、私自身も2022年に日本語教育能力検定試験に合格し、修士課程修了を待たずに2024年7月から日本語学校で教師として働いています。
それでも、還暦近くになってから大学院で日本語教育を学ぶ道を選んだのはなぜか──。その背景を振り返ることで、これから同じ道を考えているシニア世代の方の参考になればと思い、ここに書き留めたいと思います。
サラリーマンからセカンドキャリアへ
私は大学を卒業して以来、長くサラリーマンを続けていました。海外駐在も経験し、現地の生活ペースに慣れたことで、日本に戻って同じようにサラリーマン生活を続けるよりも、まったく新しいフィールドでセカンドキャリアを築きたいという思いが自然と高まっていったのです。
もともと語学が好きで、大学では中国語を専攻し、仕事でも英語や中国語を使う機会が多々ありました。その経験を、日本語教育に活かせるのではないかと考えたのがきっかけです。早期退職のインセンティブなども踏まえると、収入面で必ずしも十分とは言えない日本語教師の道でも、なんとかやっていけるだろうというシミュレーションが成り立ったことも大きかったです。
独学で始めた日本語教育能力検定試験対策
ちょうどコロナ禍で駐在先の仕事も落ち着いていたため、一時帰国の際に日本語教育能力検定試験の教本を購入し、YouTubeやネット情報などを活用して独学をスタートしました。海外駐在中という制約はあったものの、むしろ情報源が限られていたおかげで、教本に集中しやすかったのは幸いでした。
検定試験の勉強を進めるうちに、「もう少し体系的に日本語教育を学んでみたい」という気持ちが強くなりました。そして、検定試験を受けに一時帰国するタイミングで、大学院の入試を受けられることを知ったのです。過去問を解いたり論述対策をしたりと、検定試験の勉強と並行して半年ほど入試準備を進めました。「もし合格したら、定年を待たずに数年早く会社を退職し、学業に専念しよう」と具体的に考えるようになり、日本語教育を体系的に学ぶことで、教師としてのキャリアの幅を広げたいという思いもさらに強まりました。
大学院入試への挑戦
大学院入試の科目は、日本語教育に関する論述問題と外国語(私は中国語を選択)でした。日本語教育に関する知識は付け焼き刃に過ぎませんでしたが、日本語教育能力検定試験の勉強で培った知識が論述問題にも大いに役立ちました。検定試験は選択式が中心ですが、学習内容自体は論述の範囲とほぼ重なっているためです。
また、外国語試験は研究に必要な文献を読みこなす力を問うため、和訳問題のみが出題されると聞いていました。ただ、大学のサイトには著作権の問題から過去問が公開されておらず、大学の事務所で閲覧する必要がありました。しかし、コロナ禍で海外との往来が制限されていたため、実際に過去問を見られたのは試験直前。とはいえ、今までの蓄積でどうにかなるだろうと考え、特別な対策はしませんでした。
結果的に、日本語教育能力検定試験も大学院入試も無事に合格。そのうえ、勤務先の会社が「学び直し」を支援する制度を導入していたため、一定期間は給与が保障される休業を認めてもらえることになりました。こうした好条件も重なり、いよいよ大学院に進学する決断を下したのです。
これから始まる新たな一歩
今は「人生100年時代」といわれるようになり、還暦が近くなってからでも新しい世界に飛び込む選択肢は十分にあると実感しています。次回のブログでは、大学院でどのような学びがあったのか、その中で得られた気づきや経験についてお話ししたいと思います。日本語教師を目指す方やセカンドキャリアを模索中のシニア世代の皆さんに、少しでも参考になれば幸いです。